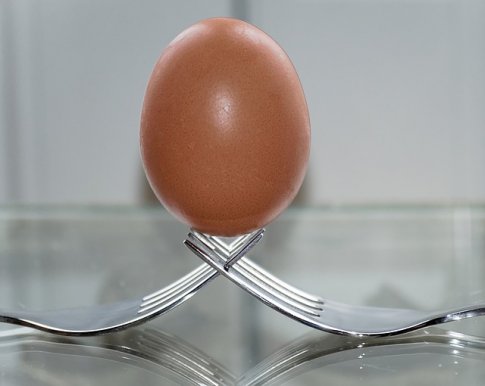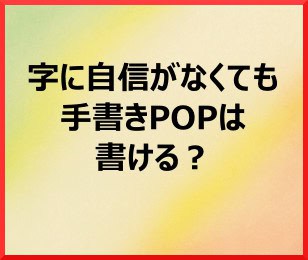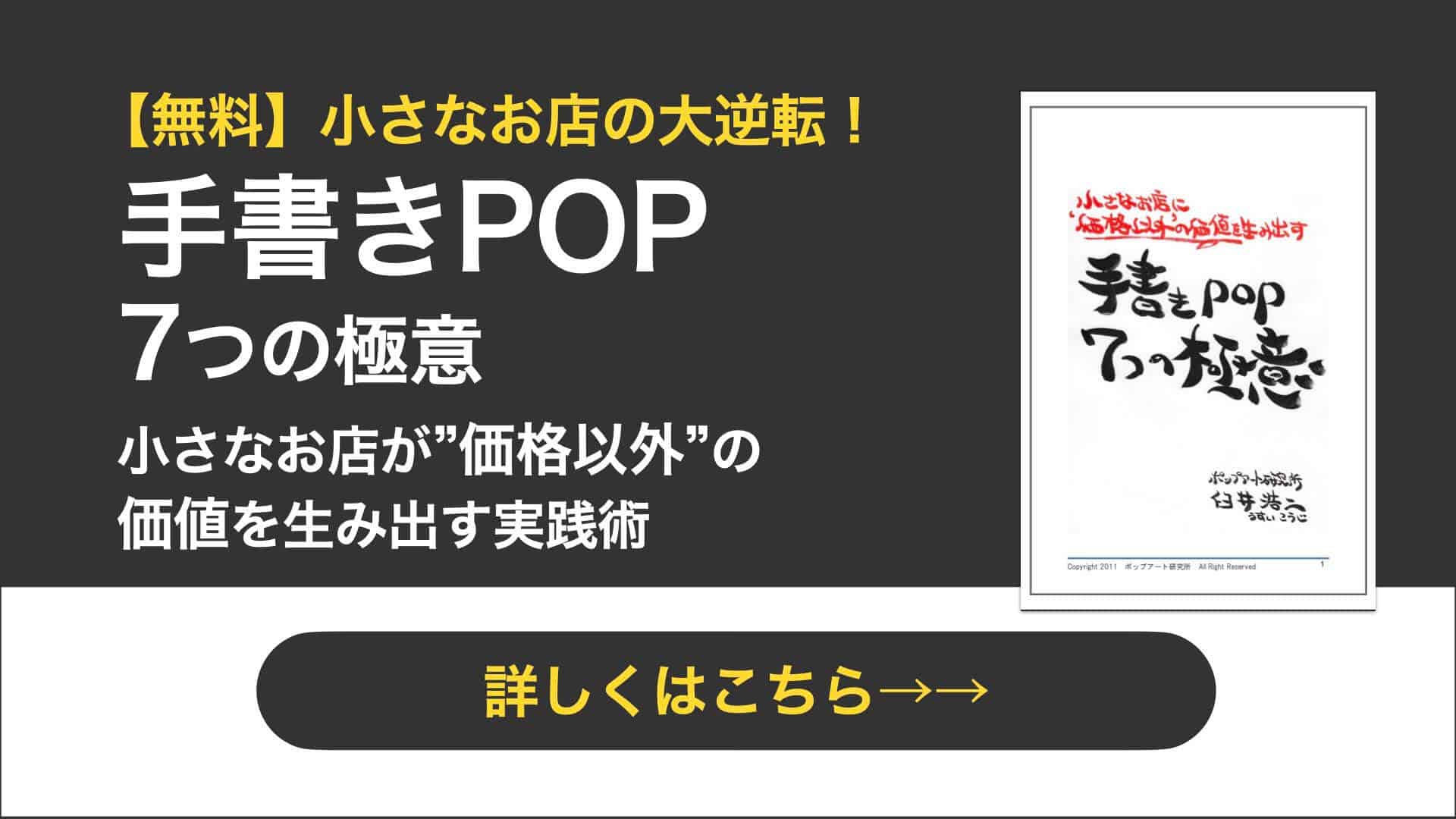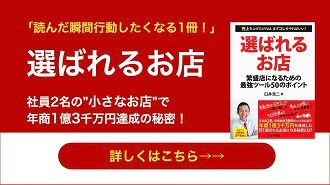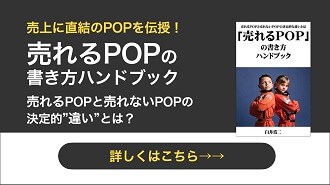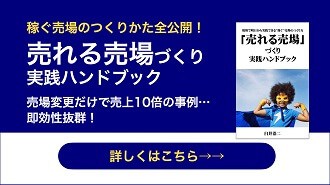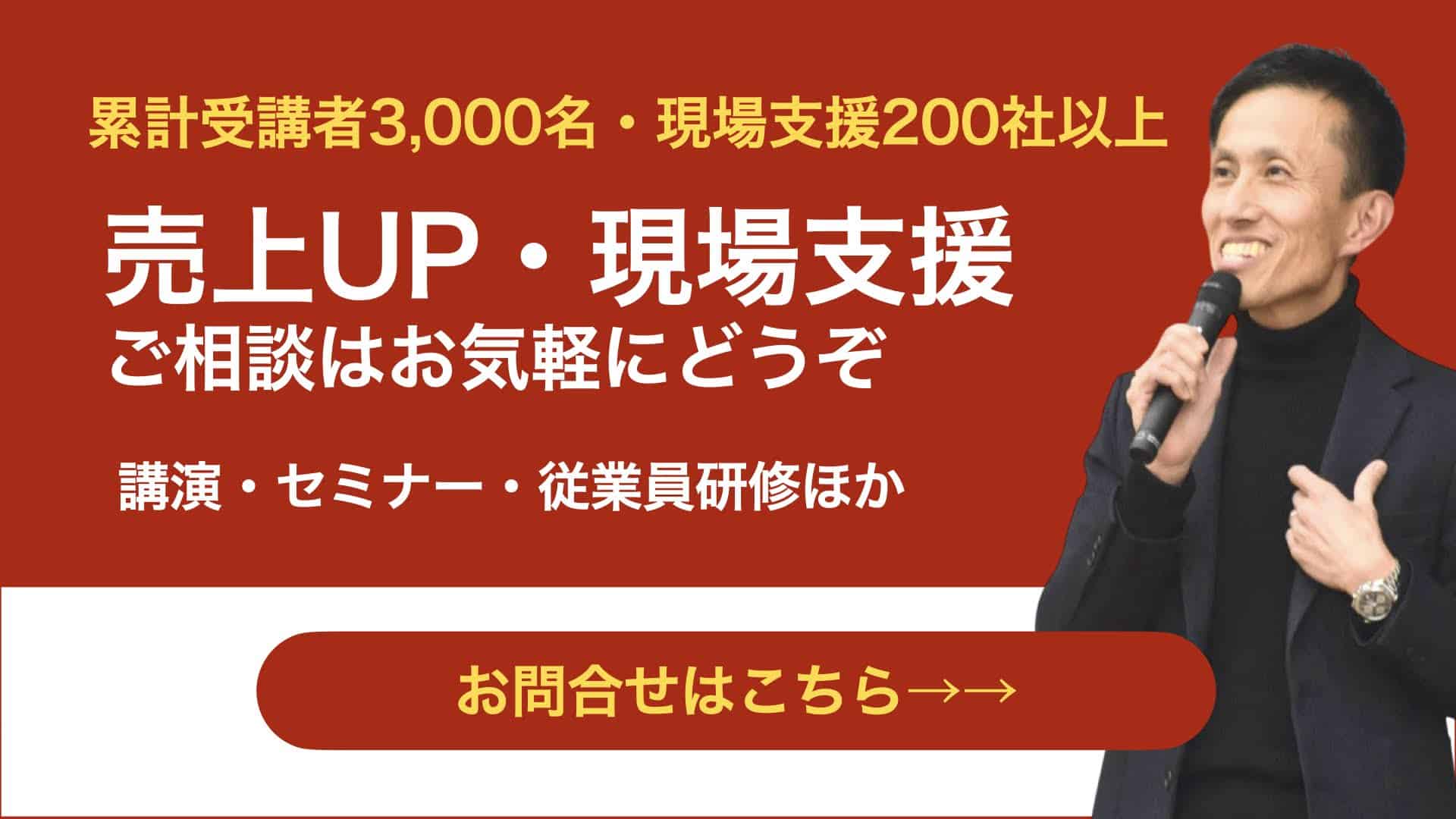チラッと昨日、フェイスブックでもつぶやいたんだけど。
農産物を販売する直売所っていうお店。
生産者の名前が書かれた野菜とか果物が売っていて、道の駅みたいな雰囲気のお店です。
(・・・何となくイメージつきます?)
農協が運営していたりが多いかな。
その直売所ね、僕も仕事で関わることが多いんで調べたんだけど、全国で1万6千店舗くらいあるそうです(農林水産省/直売所調査より)。
その数は、少し前のデータになりますが、コンビニ最大手セブンイレブンをも凌ぐ店舗数。
でね、その直売所。
それくらいの数があると、どこのお店も同じように見えてしまう。
売られているのは、キホン生産者がつくった農産物が主体なんで、ほぼ同じなんですよ。
キャベツ、白菜、トマトといった野菜や果物が商品の主。
なので、そこで他店との違いを出すのは結構タイヘンなんです。
コストをかけて、よっぽど変わった店構えにしている直売所。
立地のイイお店とかだったら別だけど。
ほぼ、どこも同じようなお店に感じられてしまうこと多いんです、お客さんからすれば。
でもね、それって、お店にしたらあまりよろしくないコトですよね。
他店との違い。
お客さんへ感じてもらわないとイケません。
・・・じゃあ、どうやって行えばイイのか?
どうやって、他店との違い。個性を出していくか?
じつは、この部分って、すごく他業種でも学べること多いです。
「直売所だから、、、」
っていうのではなくて、小売店とか他の業種でも充分に当てはまる。
例えばね、売り物(商品)で差別化ができないとしたら、、、
どうやって、他店との違い。
自分のお店独自の個性を出していくか?
その1つの方法が、手書き販促です。
そう、手書きPOPを書くんです。
例えば、こちらのPOPは昨日、販促サポートに入ったお店で書かれていた手書きPOPです。
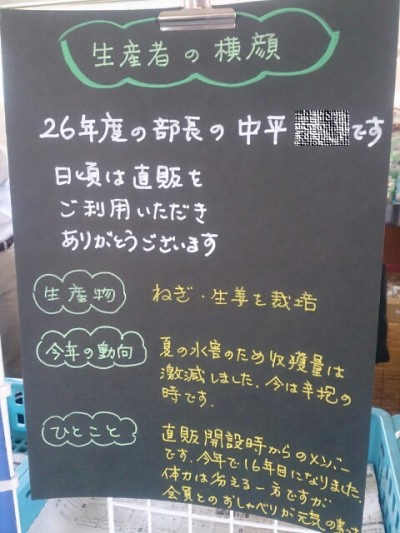
手書きPOPをすると、それだけで個性(ウリ)が生まれる
手書きPOPをどんどん書く。
そして、デキればお店の売場中に置いていく。
「・・・こんなに要らないんじゃない?」
って、感じるくらいに書きまくる。
すべての野菜、生産者さんについてを書く感じ。
・・・すると、どうなるか?
「このお店はなんか、オモシロいお店」
「POPの変わったお店」
「今度、友だちを連れて行きたいお店」
になるんです。
お客さんの中でのラベル、印象が書き替えられる。
”野菜を売っているお店”。
”野菜の安いお店”。
から、
”野菜を売っている、POPの変わったお店”
”今度、友だちを連れて行きたい、チョット変わった、野菜の安いお店”になるんです。
本当です。
・・・10年前、僕が働いてた大阪で働いてた産直店も、まさにそんな感じでした。
手書きのPOPやニュースレター(●●だより)をどんどん書いた。
お店の売場にどんどん置きました。
結果、
「なんか手書きで書いた変わったモノが置いている、新鮮・安心の野菜を売っているオモシロいお店」
そんなイメージを持っていたお客さん多かったと思う。
(↑長過ぎのイメージ、、、ですが(笑))
でもね、それで、友だちを連れて来てくれていたお客さんも多かった。
もう今は、販売する商品で他店と差はつけられない時代です。
商品での差別化って、難しい。
工夫が必要。
その1つの方法が、手書き販促。手書きPOPです。
コストをほぼかけずにデキる、お店に個性(ウリ)を創りだす方法です。


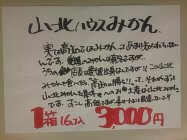
-485x272.png)