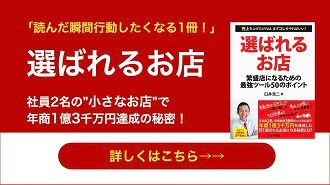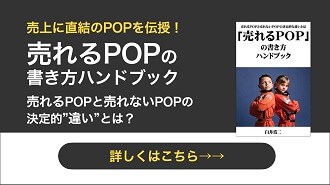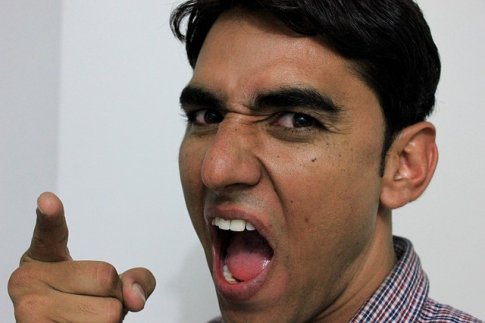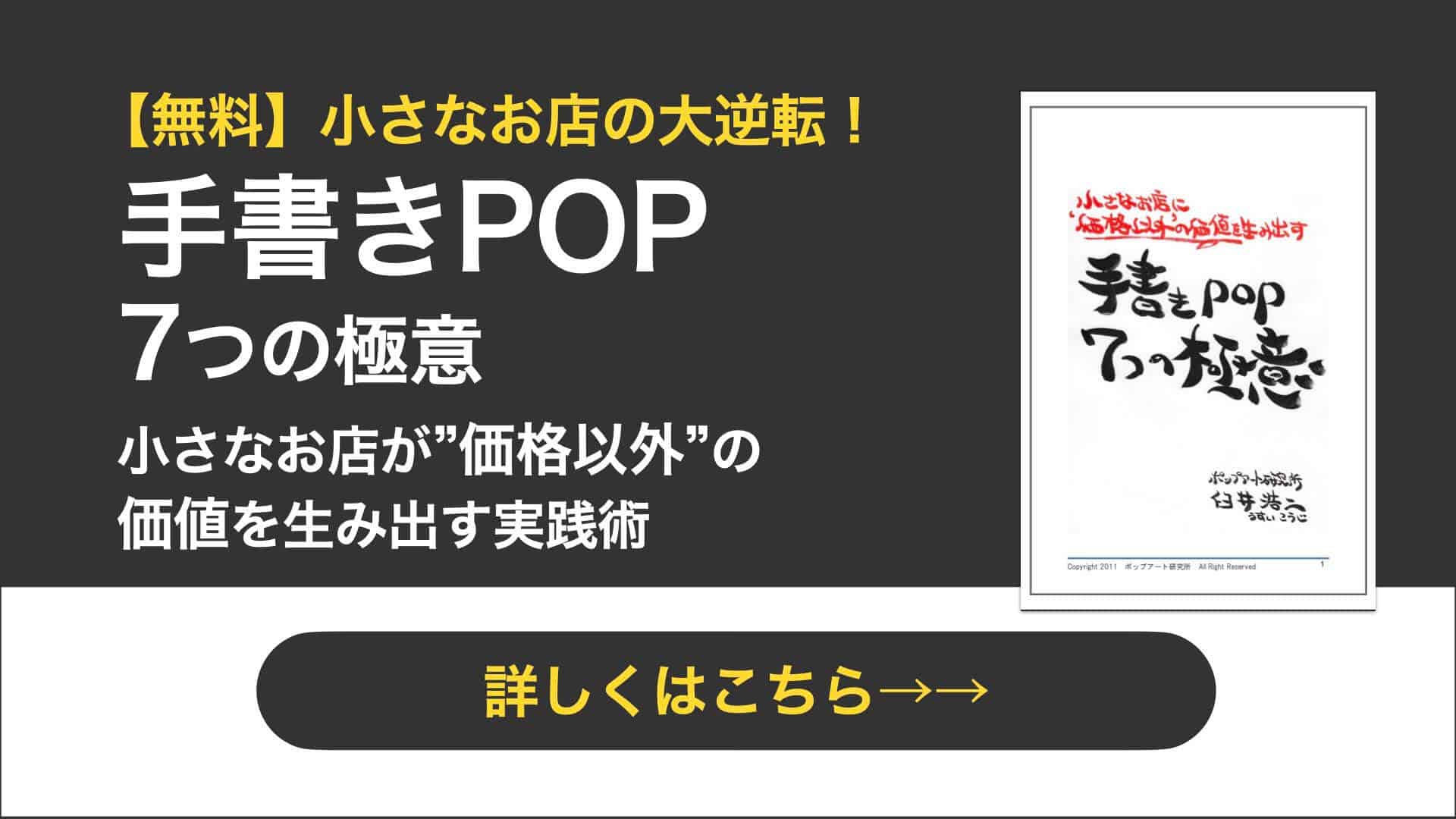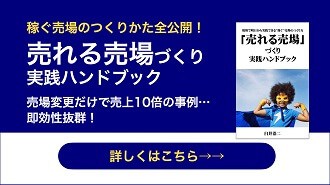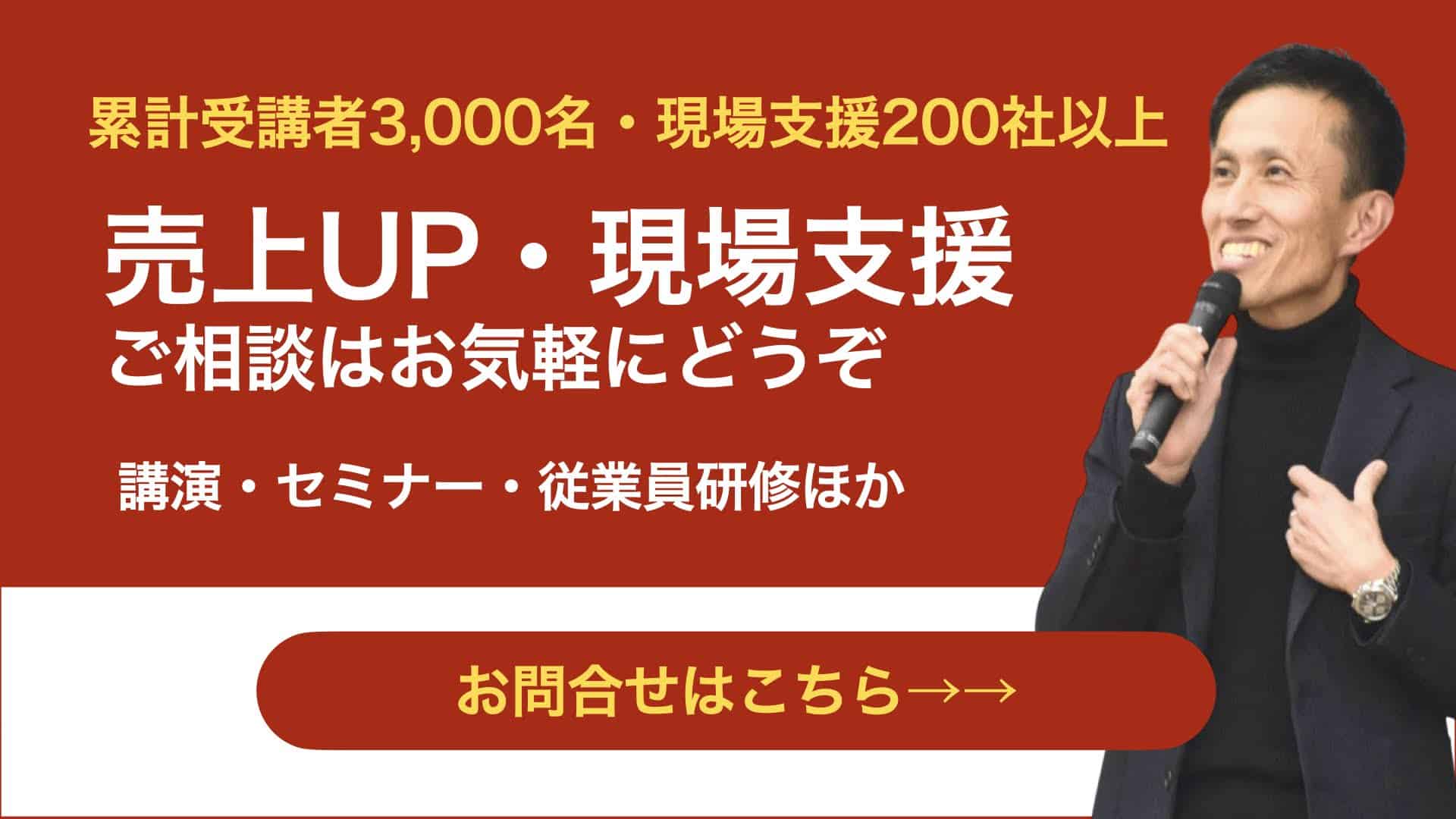昨日は、子どもの日でしたね。
うちの娘も満喫してました。
こんな感じでね^^

手書きポップが増えると生まれるメリット
手書きポップというのは、量が増えるほど効果が上がりやすい。
こんな法則があるんですね。
僕の今までの経験からいくと、お店や会社に置いてあるポップが増えてくると、
「このお店は、手書きポップのオモシロいお店」
こんな印象お客さんの頭に植え付けられる。
そして、
「手書きポップを読みたい」
という欲求が湧いてきて、お客さんは尚更、手書きポップを見てくれるようになる。
こんな黄金連鎖が起きだします。
なので、お店や会社に置くポップはどんどん増やしていった方がいい。
僕はいつも関わるお店や会社さんにお勧めしています。
っが、しかし、
臼井さんの言っていることは分かる、たしかにその通りだ。
だけど、手書きポップを書く時間がなくて、、、
という方が圧倒的なのも事実なんですね。
・・・どうすれば、手書きポップを量産できるのか?
1つの乗り越えなきゃイケない課題です。
読書と同じやり方で解決する
昨日、読んだ本にあるイイことが書かれていました。
妻が買った本なんだけど、僕も借りて読んでみたんです。
(「読んだら忘れない読書術」~樺沢紫苑さん)
・・・なんといっても、僕は読書が大の苦手。
本を読乱して10分もしたら、睡魔が襲ってくる癖があって(笑)
なので、ちょっと興味があって、娘が庭で遊んでいるスキに読んだんです。
そこに書かれていたことの1つに、
読書はチョットした空いた時間を有効に使うことがコツ
10分、15分の空いた時間に、スマホをいじるか?
読書をするか?
大きな違いが生まれる
というようなことが書かれていたんです。
これ読ませてもらった時に、思ったんです。
「手書きポップと同じやん!」って。
レジのスキを見て書いていた
10年くらい前に僕が働いていた産直店、
僕はそこでたくさんの手書きポップを書いていたんだけど。
小さなお店で、スタッフ(パートさん)もそれほど多くなく。
シフトにもよっては、僕がレジに立たなきゃいけないことも多くてね。
当然、机の前に座ってポップを書く時間なんて、全然なかったんです。
日々、レジの前で、お客さんの応対に追われてました。
そんな状況で、なんとか手書きポップを量産していたやり方。
どうしていたか?というと、、、
レジでお客さんの会計を済ませるでしょう。
っで、次のお客さんがまたレジに来られるまでの時間。
その時間に、ポップを書いてました。
お客さんの状況(売り場)を見渡しながら、
「大丈夫そうだな、」
って思ったら、さっと紙をレジ台に置いて書いていました。
(ほんと言うとね、マナー的には・・・かもしれないんだけどね、やってました)
細切れ時間をつかう
お客さん相手のお仕事をしていたら、まとまった時間って中々取れないと思うんです。
座って、それこそ、デスクワークするような時間。
だったら、チョットでも空いた時間があれば、そこを有効につかう。
次の予約のお客さんまでに3、4分でも時間がありそうだったら、そこをつかう。
お客さんが売り場を見回っている。
特に、こちらにも用事がなさそうだ。
そんなスキがあったら、手書きポップを書く時間に充てる。
1つの方法なんじゃないかな、って思います。
僕自身、なかなか読書ができない人なんで、そうしようと思っています。
チョットした空き時間。
テレビを見るんじゃなくて、スマホをいじるんじゃなくて、本を片手に読んでみよう、ってね。
意外とイケそうな気がしています^^