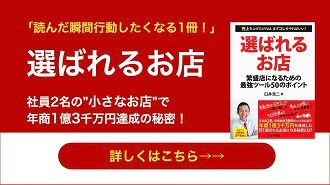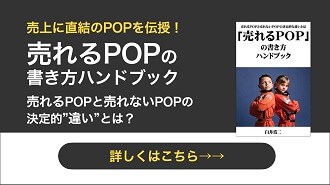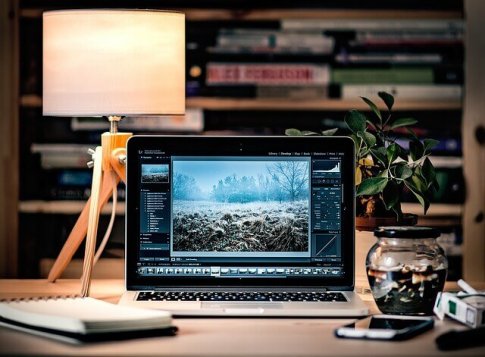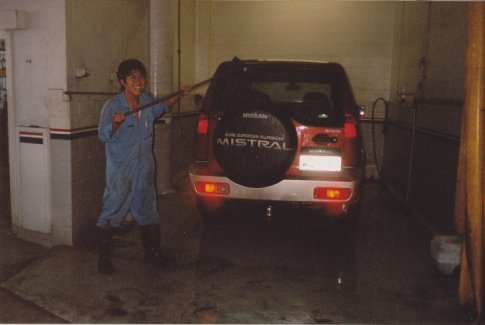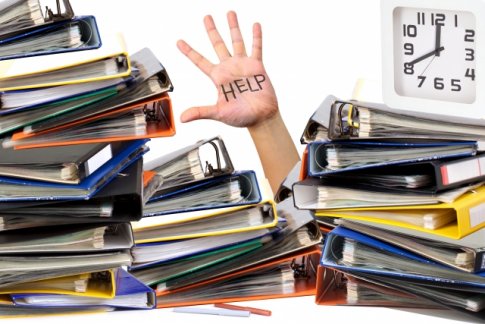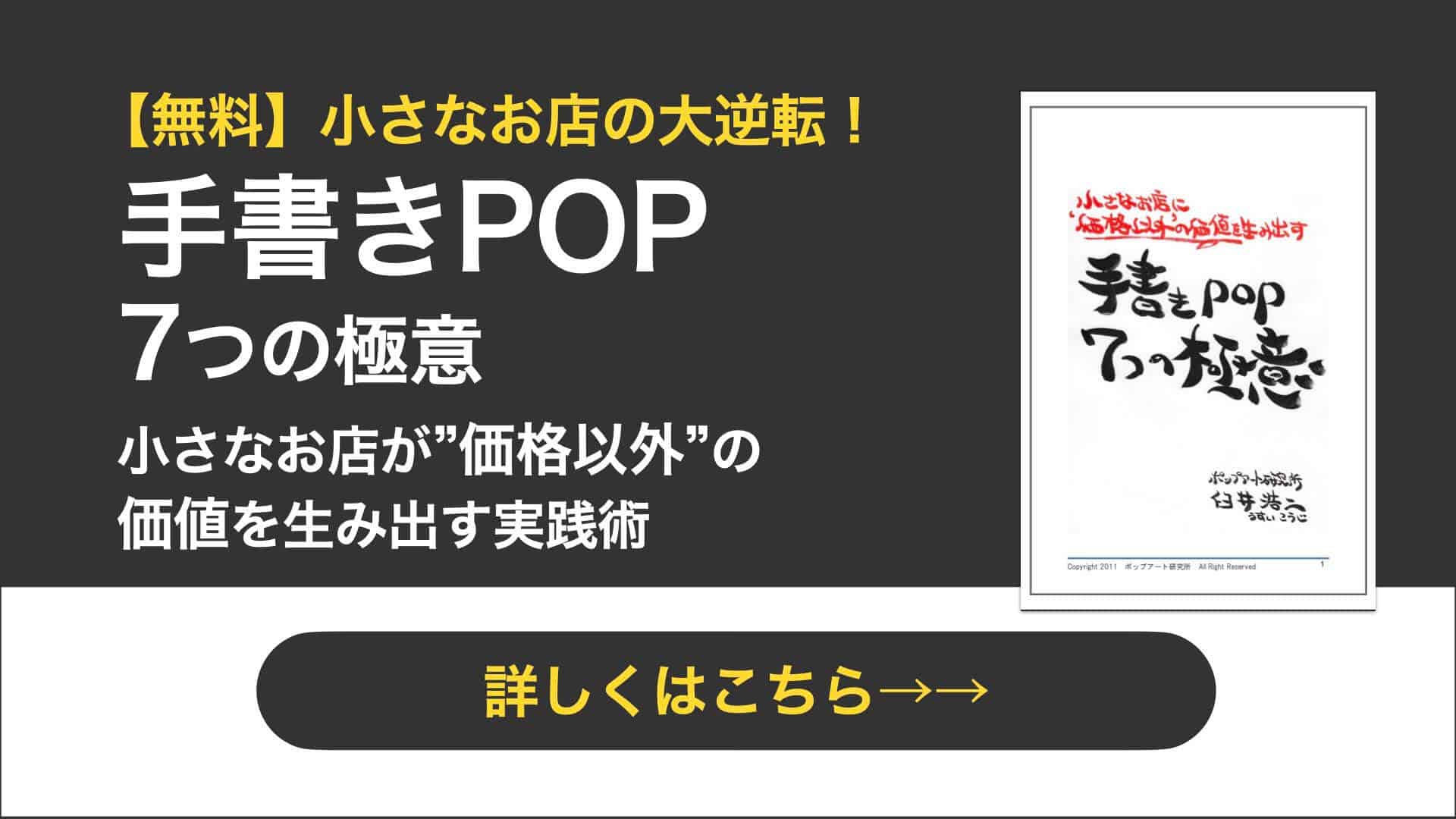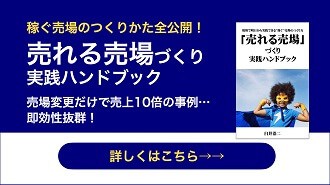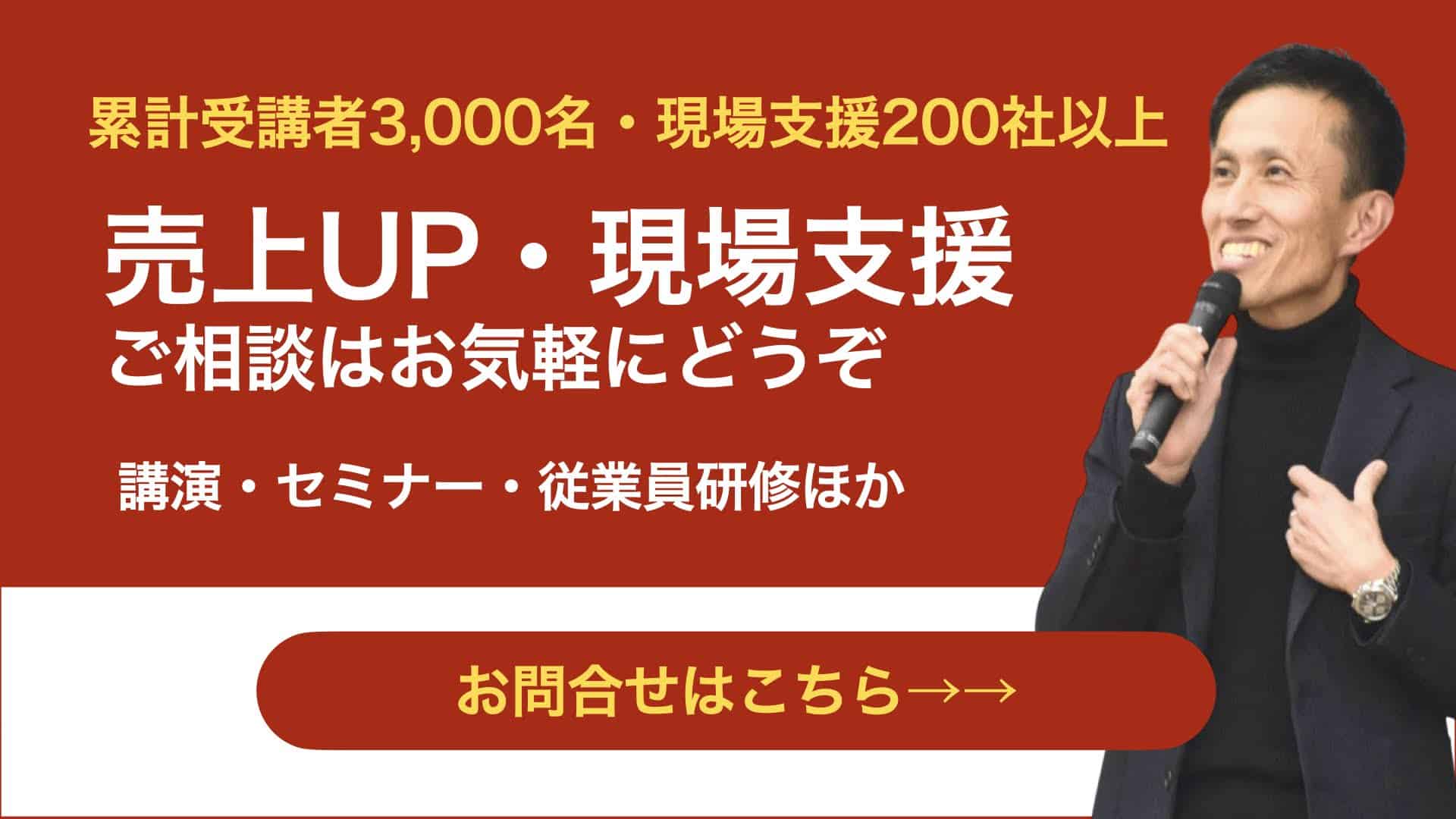今日のテーマは、チラシです。
ご質問をメルマガ読者さん(※)から頂きました。
(※POPの書き方7つの極意ご登録者へお送りしています)
1つのチラシにつき、どのくらい反応があればそのチラシに効果があったといえますか?
チラシを撒いていて、効果があったチラシとそうでないチラシの見極め方です。
ずばり結論から言うと、効果があったか?
効果がなかったのか?判断するのはご本人である、あなたです。
「センミツ」という言葉を業界でよく使われていたそうですが(今もかな?)、1,000枚チラシを撒いて3件反応があればOKという意味らしいです。
ただ、「そのチラシの反応率が何%」というのは、あんまり関係ない。業界や販売商品の単価や性質によっても違ってきますよね。住宅会社さんのチラシとサプリメント会社のとでは、反応率が違って当然です。
チラシ効果のある無いを判断する上で重要なのは、費用対効果です。
数字で判断しよう
どれだけチラシの反応率が良くても、費用対効果が悪ければ意味がありません。効果のないチラシです。
逆にいえば、どれだけパーセントが悪くても収益が取れていれば、効果のあるチラシです。あくまでも、収益という数字でチラシは判断しなければならないのではないでしょうか。
例えば、あなたが1万枚のチラシを撒いたとします。印刷代も含めて5万円かかりました。
そこから30人の新規のお客さまが、来店してくださった。チラシの反応率は、0.3%です。(冒頭のセンミツというあれですね)
業界の常識からいえば、「反応がある」なのかもしれません。ただ先ほども言ったように、
重要なのは費用対効果。
来店して下さったお客さまが、仮に1,000円の商品をサービスを購入して下さった。であれば、ここでの費用対効果をみてみると?
- 売上:30人×1,000円=3万円
- 経費:5万円(チラシ代)
- 収益:3万円ー5万円=-2万円
結果、2万円の赤字です。
反応率0.3%という数字が出ていても、収益面でみると赤字。話になりませんよね。継続できません。
結果、「効果のない」チラシになります。
忘れてはいけない視点
ただここでチラシを撒く時に、意外と見過ごしてしまう視点があります。この視点を抜きにしてチラシ販促をしては、収益は一生上がりません。
どういう視点なのか?
例えば、先程の例でいうと、5万円の経費をかけて1万枚のチラシを撒いた。すると、30人の来客があって、3万円分のサービスの注文があった。
この時点では、2万円の赤字です。
ただしかし、この30人の新規客のうち半分の15人が再来店してくださった。1ヶ月後に今度は3千円の商品を購入して下さった。
さて、このときの収益はどうなるのか?(…この辺りの計算が出てくると、面倒な方も出てくると思いますが(苦笑))
意外と見落としがちな盲点
収益を計算してみると、
- 売上1:30人×1,000円=3万円
- 売上2:15人×3,000円=4万5千円
- 経費:5万円(チラシ代)
- 収益:(3万円+4.5万円)ー5万円=2.5万円
結果、2.5万円の黒字です。
反応率は、先程の0.3%と同じ。ただ『リピート』という視点が加わったことで、収益に的に黒字になりました。
実はこのリピートという視点、
チラシ販促をおこなったときに意外と盲点になりがちです。
リピートという視点が無いままチラシの結果を見ていると、「あーぁ、反応悪かったな。赤字やん。このチラシはあかんわ。」
チラシ販促を止めていたでしょう。
一方、リピートの視点を持っていれば、2.5万円の黒字になる。
「よし、暫くこのまま続けてみよう」
収益を上げ続ける結果になったのかもしれません。
効果のある無しは、トータルで
冒頭のご質問、
どのくらいの反応があったらチラシが効果があるといえるのか?
商品や業種によってもこの数字は違ってくる、と話しました。
要は、「あなたが販売する商品がリピート性のあるものなのか?」によっても違ってくるという事ですね。
あるいはチラシを撒いて、「どれくらいの数のお客さまがリピートして下さるのか?」トータルで見ていかなければいけないという事もであります。
またテーマがずれるので別の機会に話しますが、極端にいえば、あなたのお店にリピートする仕組みがあれば、それだけで強い。収益が上がりやすくなる、と言えます。
チラシ販促を行えば、トータルで数字を追いかける。
目の前の数字だけを見ていると、せっかく収益が上がる取り組みなのに、みすみす手放してしまう…という事にもなりません。
チラシ効果のある無いを判断する上で重要なポイントは、費用対効果をトータルで見ることです。